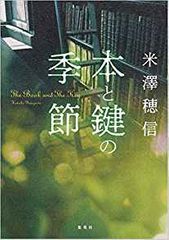人気ミステリ作家が明かす創作の「型」とスタート地点
出版界の最重要人物にフォーカスする「ベストセラーズインタビュー」。
第105回の今回は、昨年12月に刊行された最新作『本と鍵の季節』(集英社刊)が絶好調の米澤穂信さんが登場してくれました。
『本と鍵の季節』は、利用者のほとんどない放課後の図書室で当番をつとめる高校2年生の二人、堀川と松倉が、図書室に持ち込まれる謎や身の回りで起きた事件の解明に挑む作品集。団結して推理を進めるわけではなく、かといって別行動でどちらが先に真相にたどり着くかを競うわけでもない。二人の微妙な距離感が高校生っぽくてクセになります。
今回はこの作品の成り立ちや、米澤さんが得意とするミステリ小説について、そしてご自身が影響を受けた本についてたっぷりと語っていただきました。
(インタビュー・記事/山田洋介)
■創作のスタートになるミステリ小説の「型」とは
――ミステリ作家の方がどういうプロセスで作品を作り上げていくのかに興味があります。構想は小説のどの部分から始まるのでしょうか。
米澤:時々「こういう話を書こう」というようにストーリーを先に思いつくことがあるのですが、こういう場合はミステリとしては空中分解してしまうことがあるんです。
やはりミステリの出発点は「何が謎か」というところだと思っています。時々、これから書こうとしている小説について「悪い話じゃないけど、でも何を解く話なんだろう?」と自問して、プロットを練り直すことがあります。
――ということは「謎」部分から始めて、そこを中心にストーリーを作っていくということですか?
米澤:ミステリとしての「謎」と、小説としての「ストーリー」が別個にあって、それぞれの最適な組み合わせを考えていくイメージですかね。
ミステリには「型」があるんですよ。「フーダニット(Who done it)」ですとか、暗号もの、密室もの、アリバイもの、誘拐ものなどです。
もちろん一つの小説が完全に一つの型に収まるわけではなくて、暗号ものでありながらも誘拐ものであったり、フーダニットでありながらアリバイものであったり、いくつかの型の要素が混じっていることもあります。こうした型を踏まえて、じゃあ今回はどんな型なのかをイメージすることが小説を書く最初の手助けになることは多いです。
――言われてみると、確かにミステリにはいくつかの型があるような気がします。
米澤:実は、今回の『本と鍵の季節』は当時担当編集だった方に「色々なミステリの型を書いてください」と言われて始めたんです。
江戸川乱歩は『類別トリック集成』という本で、過去に書かれたミステリをタイプごとに分類しています。これはあくまでミステリの辞書的なものなのですが、同じことを小説の形でやってみませんかと言われました。それが今回の作品の元になっています。
――型というと無機質な印象を受けますが、本を読んでみると登場人物が生き生きとしていてそれを感じさせません。
米澤:書いているうちに松倉と堀川が面白いから、彼らの先が見たいと編集部の方に言っていただいたので、彼ら二人の物語ということでシリーズにしつつ、当初の案であるいろいろなタイプのミステリも書くというように両立させて書いたつもりです。
第一話の「913」は暗号もので、第二話の「ロックオンロッカー」は「九マイルは遠すぎる」というハリイ・ケメルマンの小説の型になります。第三話はアリバイもの、という感じですね。
――ミステリの「型」についてお聞きしたいのですが、新しい型はもう生まれないのでしょうか?
米澤:型については考え尽くされているということがもうずいぶん前から言われていますし、実際新しい型を作るのはすごく難しいことは確かです。ただ、もう絶対新しいものは生まれないかというと、そんなことはないと思っています。
――型とは違いますが、テクノロジーの進歩によって新しい種類のお話が生まれるということはありえそうです。たとえばIoT製品が本格的に普及し始めたなら、自動車の制御システムを外部からハッキングして意図的に事故を起こすとか…。
米澤:そういうのはあるかもしれませんね。ただ、最先端の技術なり製品は古びるのも早いので、あんまりすぐに採り入れるのは躊躇してしまうところはあります。今回の本でも「スマホ」というワードは使っていないんです。もしかしたら2年後には新しい製品が誕生していてもう誰もスマホという言葉を使っていないかもしれないので。
それと、最新技術を取り入れてミステリを書いた時、それを読者が理解できるかという問題もありますよね。古いものなので今も有効かわかりませんが、ミステリの約束事に「ノックスの十戒」というのがありまして、その一つに「未発見の毒薬、難解な科学的説明を要する機械を犯行に用いてはならない」とあります。
たとえば殺人事件などでも、未知の毒や未知のテクノロジーを使ったから可能だったのだ、としてしまうと読者がしらけてしまうというわけです。また、読者が自力で謎を解く可能性もありません。
「ノックスの十戒」を「最新技術を使ったミステリ」の話に当てはめることの是非は置いておいて、最新技術を使ってミステリ小説を書くとなると「読者が自力で謎を解くことができる」というミステリ小説としてのフェアネスを確保するのは大変だと思います。
――読者がついてこられなかったら意味がないですからね。
米澤:ただ、不可能ということではないです。たとえば「シャーロック・ホームズ」シリーズでは「同じ指紋を持つ人間はいない」という、当時解明されはじめていた事実が取りいれられていたりしますし。
――米澤さんご自身は新しいミステリの可能性について考えることはありますか?
米澤:新しい面白さはどうやったら生み出せるのかというのは常に考えています。ただ、テクノロジーについていくという意味ではあまり考えてないですね。
(第三回 ■理想の小説は「知」と「情」が和解するもの につづく)
(第一回 ■『本と鍵の季節』執筆に生きた「実体験」 を読む)