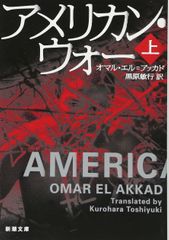報復は国も宗教も関係ない普遍的なもの オマル・エル=アッカドインタビュー(1)
出版業界の最重要人物にフォーカスする『ベストセラーズインタビュー』。 第93回目となる今回は、デビュー作『アメリカン・ウォー』(上下巻/新潮社刊)がアメリカ国内で評判となり、邦訳版が発売、そして初来日を果たしたオマル・エル=アッカドさんが登場してくれました。
『アメリカン・ウォー』は2070年代から2080年代という近未来のアメリカを舞台にしたディストピア小説。化石燃料の使用禁止に反発した南部三州と北部州の間で勃発した「第二次南北戦争」に翻弄される主人公サラットと南部の人々が骨太な筆と巧みな構成で描かれます。
続発するテロや拷問、武装組織に強く惹かれる若者たち…。デビュー作にしてコーマック・マッカーシー『ザ・ロード』と引き比べられるほどの傑作『アメリカン・ウォー』がどのように生まれたのか。オマルさんにお話をうかがいました。 (インタビュー・記事/山田洋介、撮影/金井元貴)
■報復は国も宗教も関係ない普遍的なもの
――オマルさんはこれまでジャーナリストとしてキャリアを重ねてきました。『アメリカン・ウォー』のお話をうかがう前に、今回小説を発表した理由についてお聞かせ願えますか。
オマル:ジャーナリズムでは答えが出せなかったり、ジャーナリズムの方法では表現できない問題を突き詰めたいと思ったんです。
一人の人間がどんなふうに過激派的な思想を持つのか、そしてどのように過激な行動に及ぶのかといったことには決まった答えがありませんし、個人の内面のことですからジャーナリズム的な手法では表現できません。となると、ノンフィクションではなくフィクションの形をとって探索するしかない。それが今回小説を書いた一番の理由です。
――アメリカで起きた「第二次南北戦争」を舞台に「報復の連鎖」が大きなテーマとなっている小説です。このテーマを選んだ理由はどんなところにありますか?
オマル:「報復」は今の世界にひとしく蔓延している、ある意味普遍的なものです。その国や場所によって宗教も文化も違いますが、どのように報復を誓う気持ちが生まれるかというのは、おそらく皆同じでしょう。
たとえば、アフガニスタンに空爆をしても、アメリカのど真ん中に空爆をしても、生き延びた人は同じ感情を持つはずです。どこに住んでいるどんな人であっても、不正義と思われることをされたら、同じような気持ちになり、そして同じような行動をとる。
私たちはどうしても地球の反対側にいる人は、考え方も行動もまったくちがうんだと考えがちですが、そうではないんだというアイデアが、こういうテーマに結びついたんだと思います。

――「報復」というテーマについて。この作品では、たとえば主人公のサラットが物語の最後で報復の無意味さや不毛さに気づいて、計画していた報復的行動を取りやめる、といったことにはならず、報復は完遂されます。こうすることによってどんなことを表現しようと思ったのでしょうか。
オマル:この作品については、エンディングがどうなるかというのは比較的早い段階からイメージができていました。ただ、書き進めるうちにもう少しハッピーなエンディングの方がいいんじゃないか、そちらの方向に転換したほうがいいかもしれないという気持ちに駆られたのは事実です。
一方で、「こういう状況に置かれたら、人はこうするだろう」という自然な成り行きをしっかり書ききる責任も感じていましたから、結局は当初イメージしていたようなエンディングにしました。
付け加えるなら、サラットが報復の不毛さに気づいていなかったかというと、そんなことはないと思います。その無意味さは十分にわかっていたはずですが、彼女の場合は「報復」だけでなく「世界のすべて」を不毛なものだと感じていたでしょう。だから、彼女が成し遂げた報復は、特定の誰かへの報復ではなくて、世界全体に対しての報復だったんです。
最後の場面のサラットは「悪の化身」になっていますから私自身好きではありませんが、この小説で私が目指したのは「イノセントな人がどうキラーになっていくのか」という変化です。
その意味では、読者を感動させたり共感させたりといったこととは逆の方向を向いて進んでいたわけですが、どうしてサラットがこうなってしまったのかは読者が理解できるようにしたいという気持ちはありました。
――そのサラットは、身長が190cm以上もある、かなり体格のいい女性です。そして自分のいるアメリカ南部と対立する北部軍の高官の命を狙う。この設定であればサラットは男性でもよかったのではないかと思ったのですが、サラットを女性にしたのにはどんな理由があったのでしょうか。
オマル:二つあります。一つは、作品冒頭で彼女がまだ幼かった頃に自宅である貨物コンテナの前で蜂蜜の容器を手にしているイメージが明確に見えていたことです。この少女が中心的なキャラクターになることは、書き始めた時からはっきり認識できました。
もう一つは、過激派的な思想を持つ人が登場する話や、そういった人がどのように悪意を持っていくのかという話は、これまでほとんどが男性目線で作られたものだったことです。そこを今回女性目線で書いたことでまったく違う表現ができた箇所がいくつかあります。
その一つが拷問を受けるシーンで、男性への拷問と女性への拷問は内容も違いますし、そのシーンが与えるインパクトも変わってきます。あとは単純に、男性が主人公の本が世の中には多すぎますよね。
――作中に「戦闘鳥」というドローンが出てきます。これは北軍の兵器で、サラットたちが暮らす南部の町を爆撃する無人機ですが、実は北軍もこの「戦闘鳥」を制御できていないのではないかと南部の人々が噂しあう描写があります。これは、現在イエメンやリビアなど、ドローンが爆撃を行っている地域で誤爆の被害に遭った人々の感覚と近いのではないかと思いました。
オマル:それが私が意図したところで、イエメンやアフガニスタン、リビアで人々が経験していること、つまりいつ爆撃されるかわからない状況で生きているということをここで表したかったんです。
――実在する場所やできごとへのオマージュと読める場所がいくつかあったのが印象的でした。たとえばサラットが収監されていたシュガーロフ収容所は、米軍のグアンタナモ収容キャンプや、イラクのキャンプ・ブッカの面影があります。
オマル:シュガーロフはまさしくグアンタナモをベースにしています。グアンタナモには8回取材で行っていて、軍事演習も見ていますし収容所の中も取材しました。
あとは、作中に難民キャンプが出てきますが、そこはレバノンのシャティーラという難民キャンプの取材体験が元になっていて、作中で起きる大虐殺もこの場所で実際にあったできごとがモチーフになっています。その他にも、ジャーナリストとして見聞きしてきたことや、実際にあった出来事を元にした描写は部分的に散りばめていますね。 (後編につづく)