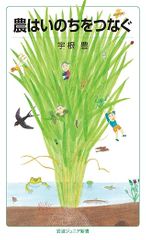日本の食卓に欠かせない「ごはん」ができるまでの膨大な「手間ひま」
毎日口に入れる食べものは生きものであり、「いのち」を頂いている。ただ、食卓の上で茶碗に盛られているご飯を食べているときに、「食べもの=生きもの」ではなく、目の前に並んでいるのは、食べるものと感じるものだろう。
現代社会で「農業」を「農業は食料を生産する重要な産業である」と説明することが多い。「農業」を「工業」に、「食料」を「製品」に置き換えても通じるし、農業と工業に違いもないように思えてくる。けれど、工業的な食糧生産という捉え方は、あまりにも人間中心の視点に偏っている。では、「農」とは何なのか。
◾️植物である「イネ」が日本の食卓に欠かせない「ごはん」になるまで
『『農はいのちをつなぐ』』(宇根豊著、岩波書店刊)では、生きものの「いのち」と私たちの「いのち」のつながりを支える「農」とは何かを、たくさんの生きものが行きかういのちの交差点・田んぼから考え、解説する。
稲が米になって食べられるまでを知ることで、食べものが生きものであったことを感じられるのではないか。冬の間、タネ(種籾)はネズミに食べられないように、倉庫の天井から袋に入れて吊り下げられている。その後、水に浸けられ、籾殻から白い芽が出ると、苗代でタネ播き。芽が出るとタネから苗に替わり、藁でくくって束にし、田植えが始まる。
田植えが終わると、稲になり、夏が過ぎると、茎の中に2mmほどの穂のもとができる。穂を出し、花が咲き、メシベに花粉がかかり、籾を閉じる。一つひとつの籾の中で米粒は少しづつ大きくなって重たくなり、穂が傾いてそのうち垂れ下がるようになる。
次第に籾に色がつき、葉も茎も養分を送り尽くして黄色くなり、田んぼ一面が秋になる。そして、稲刈りが始まる。鎌で刈り、10日ほど掛け干しし、脱穀機で籾と茎葉を切り離す。ここから稲ではなく、籾と呼ばれるようになり、籾摺機で籾殻を剥がし、玄米になる。さらに精米器で糠を削り、白米となる。このときに、胚芽もとれるので、もう芽は出ない。さらに焚かれると「ごはん」と呼ばれるようになる。
稲が米になり、食べられるまでを知ると、食べものが生きものだったのはいつ頃だったか、その時の田んぼの様子はどうだったのかと想像したりできる。そして、新米を食べるとき、新米の強い香りがきっかけになって、ご飯が稲だったことを思い起こさせてくれる。食べものが生きものだったと気づくことができるのだ。
稲や小さな虫、草などのいのちを知ることで、「農」とは本当はどういうものかがわかるようになるはず。本書をきっかけに農といのちについて考えてみてはどうだろう。
(T・N/新刊JP編集部)